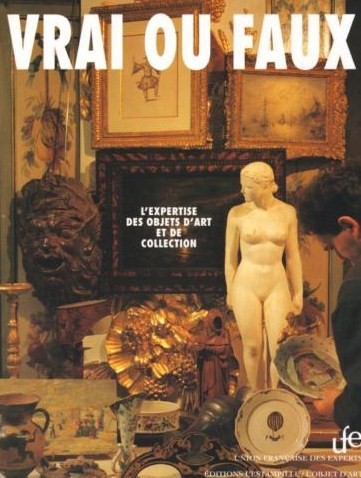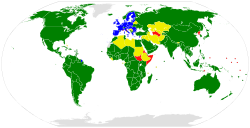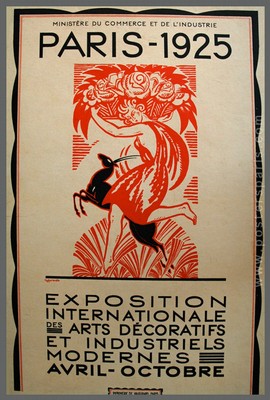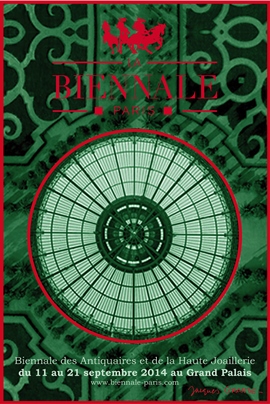美術品、骨董品、アンティーク品、と言うと、必ず「それってホンモノですか?」と聞く人がいます。
人気のTV番組『開運!なんでも鑑定団』などを見ていますと、「馴染みの骨董店で100万円で買った壷」を鑑定してもらったら5千円だった、というような結果もあり、その場合「ああニセモノだった」となるわけですが…。
「ニセモノ」を語る前に、では「ホンモノ」とは何でしょう。
たとえば、絵画。ルーベンスは分業システムで大量生産をした画家で知られています。助手200人をかかえた大工房での制作。描くのは職人、考えるのは画家、というわけで、彼の場合は構築したに過ぎず、実際に絵の具をキャンバスに当てたのは、ほとんどが助手です。それで、ルーベンスの絵画の値段は、実際ルーベンスがタッチした分量で値段が違うと言われています。
ではルーベンスの工房で、弟子だけで描かれた絵画は「ニセモノ」でしょうか?
フランスでは、美術品を売買する場合、使用される表現は法で定められています。
”De” または”Par“(~による)といった表現に続いて苗字+名前が入っていれば、それはサインがなくとも、その作家自らが手がけた作品、ということになります。
さらに”Signé …”(~とサインされている)とあれば、信憑性に更なるギャランティが加わります。
”Attribué à …”(~とされる)という表現は、その作家のものとかなりの割合で推測されるものの、ギャランティが得られない場合に使います。ギャランティとは、大家の先生が仰ること、ではなく、必ず証拠品としての文献またはそれに順ずる歴史的事実が必要になります。ただし、この文言が入っていれば、少なくともその作家と同時代の作品であることは証明されています。
”Ecole“(~派)の後に作家の名前が続く場合、実際に制作したアーティストは、巨匠の弟子であったことが周知の事実で、作風やテクニックを継いでいる、ということになります。
(なお、この表現については、制作したアーティストが存命であるか、死後50年以内でなくては使用できませんので、いくら自分がミケランジェロの彫刻を研究して作風を忠実に再現しても、ミケランジェロ派、とは名乗れません!)
”Epoque“(~時代)とあれば、その歴史的一定期間、ある世紀、ある時代にその作品が制作された証明があるということです。
”Dans le goût de“(~風の)、”Style“(~スタイルの)、”Manière de“(~派の趣向で制作された)、”Genre de“(~様式の)、”D’après“(~に倣って)、”Façon de“(~風の)、といった表現があれば、これらにはその作家や様式、時代に関する一切のギャランティはありません、ということです。Style Art Déco (アール・デコ・スタイル)とあっても、それはアール・デコの時代を証明するものでもなければ、アール・デコの様式を証明するものでもない、ということです。
”Oeuvre authentique“(本物の作品)とあれば、その作品は作家自らの手によって制作されたもの。
”Original“(オリジナル)とあれば、その作家または作家のコントロールと責任の下で制作されたもの。そのオリジナル作品が、別の既存の作品からインスピレーションを経て制作されたものであれば、その旨も記載しなくてはなりません。
技術によって、複数の作品が出来上がるものがあり、それは法で認められています。その場合、売買人は “tirage” (版)を明記しなくてはいけないことになっています。
”Reproduction“(複製)の場合は、必ず見える位置に、消えない方法でその旨を記載しなくてはなりません。また、この文言は売買証明書にも記載する必要があります。
こういった表現は、古美術品オークションのカタログを読む際に知識として最低限必要です。たとえば某オークションのカタログに、フランソワ・ブーシェ(1703-1770)の作品の評価額が50-80ユーロとあります。もちろん D’après François BOUCHER と記載されているのは言うまでもありません。このD’aprèsの意味を知らないで、「これはフランスのオークションで購入したフランソワ・ブーシェの作品ですよ」といって売りつけるディーラーがいないとも限りませんので、注意が必要ですね。
(続く)