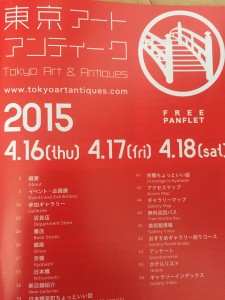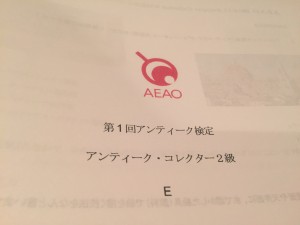アンティーク検定、今年からスタートするビギナーズ級の3級の科目にはありませんが、2級・1級には「現代時事アンティーク」という科目があります。これは英語でいうArt Marketのこと、つまりアートやアンティークの市場に関してのお話です。
欧米では、美術史の研究者がアート・コレクターとしての第一人者であったり、またアンティーク・ディーラーが大学で教えていたり、と、マーケットと学問の世界はシンクロナイズしているのですが、日本ではなかなか2つの世界が交わることはありません。学問として追求している人は、取引されている値段には無頓着だったり(絶対に身銭を切って買ったりしなかったり)、ディーラーとして品物を回している人は、実はあまり周辺の美術史に造詣が深くなかったり…。お医者さんの世界で言う「研究」と「臨床」はなかなか両方一度にはできないよ、ということでしょうか。
2014年にアンティーク検定2級を受けて合格した人の中にも「現代時事アンティーク」は難しかった、という方が大半でした。各科目の平均点でも、この現代時事アンティークはやはりみなさんの弱点だったようです。「だって教科書がないし、何をどう勉強していいのかわからない」と。
この分野は、グローバルな視点を養う意図もあり、問題の半分は海外の関係者から出題されています。残りの半分は、日本のアートマーケット専門家の方などから出題されていますが、問題に関してはすべて日本語のメディア(新聞、TV,、雑誌)で話題となったものがほとんどですので、普段からちょっとだけアートの世界にアンテナを張っていれば、キャッチできるものなのです。
とはいえ忙しい現代社会、メディアにはあらゆる情報が氾濫していて、何から何まで追えないよ、というのもむべなるかな。そういう場合は、アートフェアに行きましょう!

東京アートフェア2015
残念ながら先週末の3日間で終了してしまいましたが、東京国際フォーラム・展示ホールで開催されていたアートフェア東京などは、日本最大の見本市として、やはり規模の点でも勉強になりますし、こういったフェアでは無料の冊子なども沢山設置されていて、手にしてパラパラとめくるだけでも、現代のマーケットの傾向が掴めます。

例えばこのアートフェア東京で、「東京アートアンティーク」(2015 4/16〜18)というフリー冊子が設置されていました。めくってみるとChristie’sの広告が掲載されています。2015年上半期の東洋美術のオークション日程が書いてあるのですが(香港、ニューヨーク、ロンドン)、日本の浮世絵や新版画のオークションはオンラインで行われるのだな(東京では開催されないのだな)、といったことがわかり、そこからサイトにアクセスして・・・と、知的好奇心が広がります。
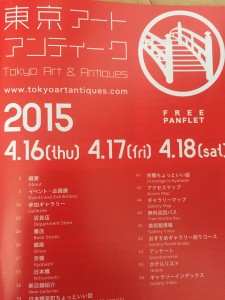

Christie’sの広告
もしかしたら出題者も同じようなことをしているのかもしれませんよ!?