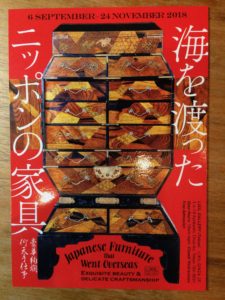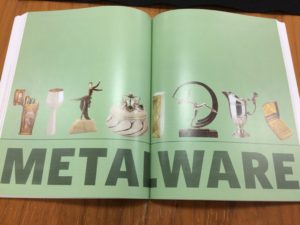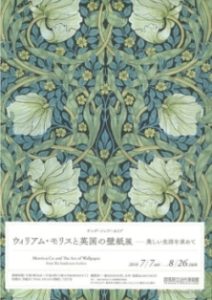パイ インターナショナルより発売されました「西洋骨董鑑定の教科書」の出版を機に、4月より毎月1回、本書をみなさんで読みほどきながら、ときにはツッこみ、ときには批評し、原書(英語)を部分的に読んで理解したり理解できなかったり・・・といった「読書会」を開催してきましたが、いよいよ最終回となりました。
今回は「コレクタブル」の章。コレクタブルとは、コレクト=蒐集するに値するもの、という意味で、その人が自分にとって価値があると思えばなんでもコレクタブルになります。グリコのおまけでも海岸に落ちている貝殻でも・・・これらはさすがに美術品とは言えませんが、それでも多くの人が欲しがれば、その価値は上がるのです。
本書によれば、コレクタブルにとって大切なのは、CARDだと言います。
C=Condition コンディション
A=Age 年代
R=Rarity 希少性
D=Desirability 入手したいかどうか
そしてさらに2つのP、すなわちProvenance(来歴)とPretty(美しさ)が加われば、それは立派なコレクタブル・アンティークになるのです・・・だそうです。
今日はアンティーク・ドール、テディ・ベア、キルトやサンプラー、そしてコスチューム・ジュエリーについて、みなさんで意見交換をしながら読んでいきました。
これらコレクタブルのアイテムも今やオークションに出品されますし、アンティーク・ドールなど何百万円もの値段がついて落札されますね。
「西洋骨董鑑定の教科書」に関する読書会は、各章ごとに行ってきましたが、いったんはこれにて終了です。また機会をみて、再開したいと思っています。
ご参加者のみなさま、本当に貴重な意見をありがとうございました。