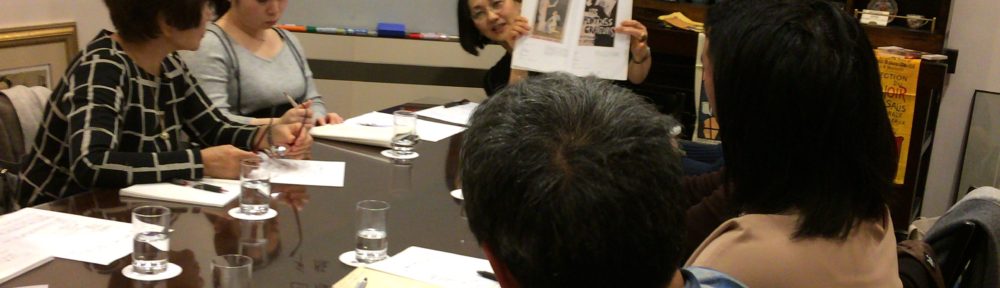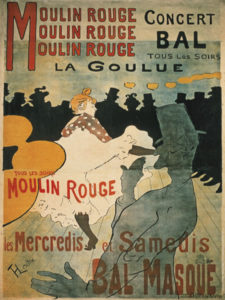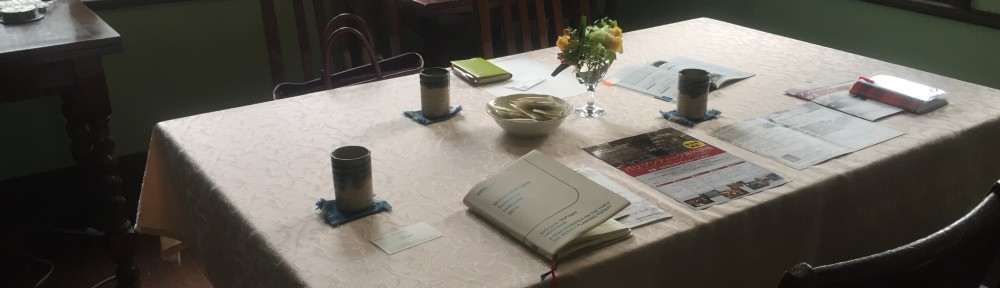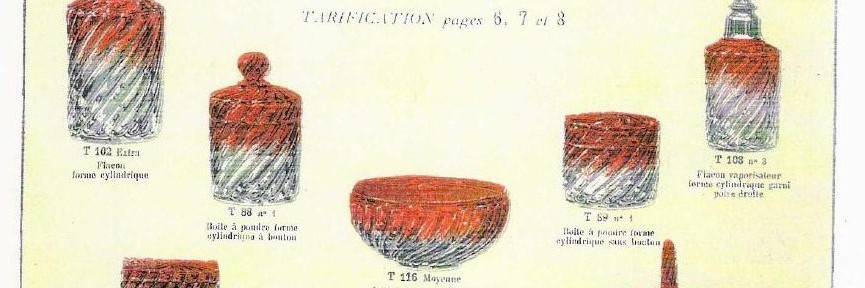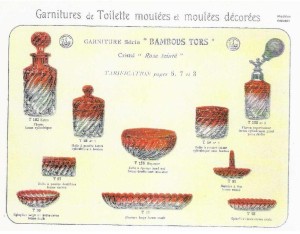本検定監修者の岡部昌幸先生は、各学会でも活躍されていらっしゃいますが、今回は中でも深く関わられている竹久夢二学会の大会につき、ご紹介いたします。
どなたでもご参加可能ですので、お時間ご都合のつく方は、どうぞおいで下さい。
日 時 : 2019年3月30日(土)
会 場 : 拓殖大学文京キャンパス国際教育会館(F館)3階 301教室 ※正門右奥古い校舎
(東京都文京区大塚1-7-1 地下鉄丸ノ内線茗荷谷駅下車徒歩5分)
***************************************************************
14:00-14:10 挨拶 竹久夢二学会顧問 小嶋光信(夢二郷土美術館館長)
14:10-15:40 学会賞受賞記念講演
下山 進 (吉備国際大学名誉教授、デンマテリアル株式会社・色材科学研究所非破壊分析研究室取締役技術顧問)
「夢二《西海岸の裸婦》の科学調査」
大原 秀行(吉備国際大学副学長、絵画修復家)
「夢二「西海岸の裸婦」の修復について」 」
15:50-16:20 研究・活動報告
小嶋ひろみ(夢二郷土美術館館長代理)
「夢二《西海岸の裸婦》修復による美術史的成果から生誕135年展に向けて」
16:20-17:00 研究発表
畑江麻里(足立区立郷土博物館専門員)
「竹久夢二の「美人画」の線 ― 現代浮世絵彫師の作品の分析から ― 」
17:10-19:00 懇親会(303教室) ※参加費無料
竹久夢二学会事務局 〒703-8256 岡山県岡山市中区浜2丁目1-32
夢二郷土美術館気付 電話(086)271-1000 fax(086)271-1730