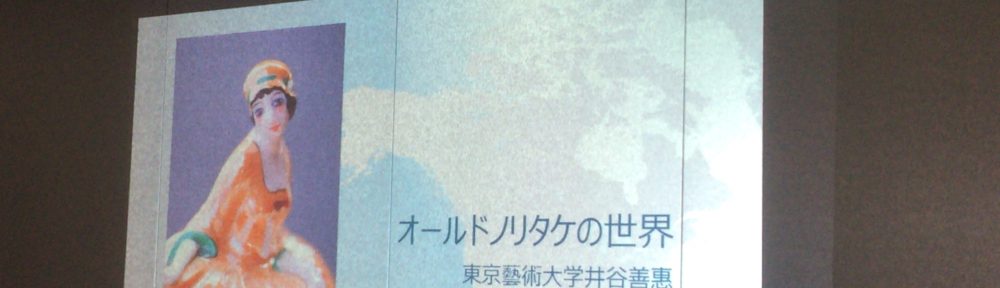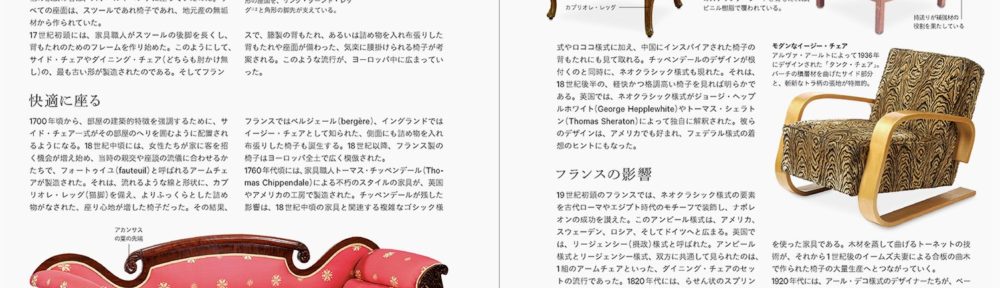7月のAEAOサロン倶楽部は、6/28〜9/17まで三菱一号館美術館にて開催される、「ショーメ 時空を超える宝飾芸術の世界―1780年パリに始まるエスプリ」 展のプレ講座として、ジュエリーの世界について学びました。
まずはジュエリーの素材と加工についてあらためておさらいします。どこまでをジュエリーと呼ぶのか、プラチナはなぜ流行らなかったのか、金と銀はどちらが先に使われていたのか、クローズド・セッティングって?ー第7回アンティーク検定・3級に、クローズド・セッテイングについての設問がありましたね。
そしてショーメの歴史上の重要人物について、ショーメ側(ジュエリーデザイナーや経営者)と権力者側(ナポレオン、ジョゼフィーヌ、マリー・ルイーズ、オルタンス、ウージェニーetc)からの視点で、19世紀のフランスの歴史と絡めて、たっぷりとお話いただきました。参加者のみなさまも、フランス史やフランス絵画に詳しい方も多く、いろいろな視点から見ていきます。
最後に今回の展覧会の構成、見どころ、特別な用語の説明(パリュール、アクロスティック・ジュエリー、シャトレーヌ・ウォッチ、エグレットetc)などについてもしっかり解説をいただき、いつ行ったら空いている?女子割の日があるの?なんて話まで、みなさんで盛り上がりました。
ジュエリーに対する価値観も、国によって、また時代によって、大きく異なっています。政変が不安定な国では、常に資産を宝石類として所持し、何かあればそれを持ってどこかに行けるようにしていたとか。お金があっても、宝飾をはじめ自分を飾ることに興味のない世代が増えている、昔と違って財力を示すバロメータとしてジュエリーはもはや時代遅れ、ティアラなんて絶対身につけることは生涯ないけれど、それを側に置いておくだけで幸せな気分になるに違いない・・・懇親会では、いろいろな意見が出ました。
ヴァンドーム広場の宝飾店は、観光でパリに行ってもなかなかおいそれと入れるところではありませんが、美術展ではこうして一流の名品が(手には取れないですが)見られるのですから、ぜひ足を運んで見ていただければと思います。