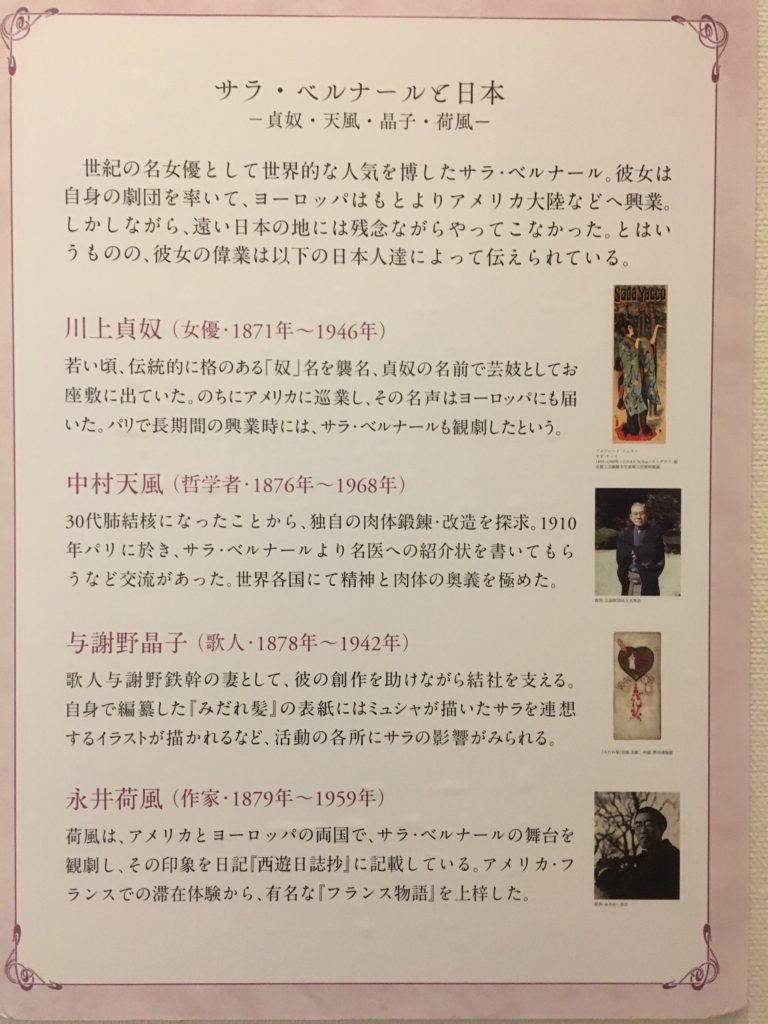10月のAEAO サロンは「チェコの可愛いデザインを求めて 〜ミュシャ、チェコ・キュビスムからチェコ・アニメまで〜」と題して、世田谷美術館で開催されているチェコ・デザインの鑑賞会を行いました。装飾工芸の世界ではミュシャは言うまでもないですが、逆にミュシャしか知らない・・・という人も多いのではないでしょうか。そんな知られざるチェコのデザインを総括した展覧会です。
見学に先立ってのプレ・レクチャー会場は、館内の公園に面したフレンチレストラン『Le Jardin』。窓の外からは緑が生い茂り、とても東京23区内とは思えない風景、日曜日とあってウェディングと思わしき団体がお庭で集っていました。
ちょうど先月国立プラハ工芸美術館を訪問された中山久美子先生(当協会アンティーク・スペシャリスト)が建築も含めた現地の様子をレポートしてくださり、またチェコという国についても歴史や政治をおさらいした上で展覧会の章立てや、チェコ・キュビスムについて詳しく解説してくださったおかげで、会場に足を踏み入れても戸惑うことなく、進んでいけます。
展覧会場は、都心の混み混みした会場とは異なって非常にゆったりとした空間構成、また場所柄や内容の性質からしても、昨今よくあるメディアにそそのかされてとりあえず話題になっているから来ましたよ、という鑑賞者はほぼ皆無、みなさんニッチに好きな人が集まっているという感じが読み取れ、非常に居心地のよい空間でした。
アール・ヌーヴォーから現代までのチェコ・デザインがだいたい10年ごとにブースで仕切られて展示されており、そこには家具ありテーブルウェアあり調度品ありポスターあり、あらためて装飾工芸という分野は、産業、デザイン、機能、この3つの軸で成り立っているのだと感じさせてくれます。
10月は台風や大雨に何度もやられ散々なお天気の月でしたが、この日は太陽も出て暑くもなく寒くもない本当に気持ちの良い日とあって、砧公園は多くの家族づれのピクニックや子供たちのスポーツで賑わっていました。普通は展覧会見学といえば結構歩くので、足も疲れがちですが、緑の中を歩くのは別腹ならぬ別筋肉でしょうか!?ぶらぶらと公園を横切りながら帰途につきました。