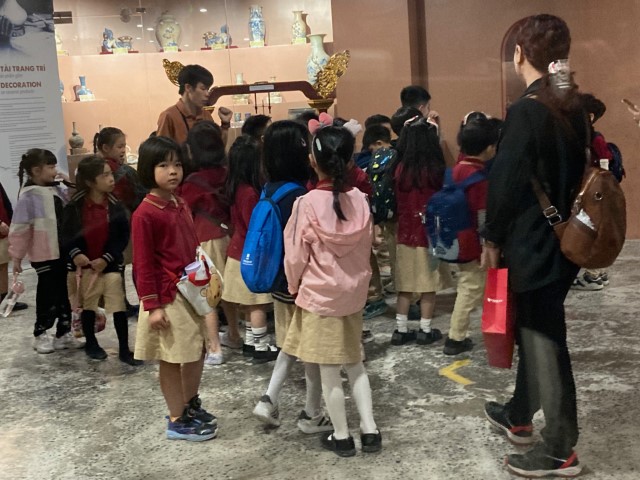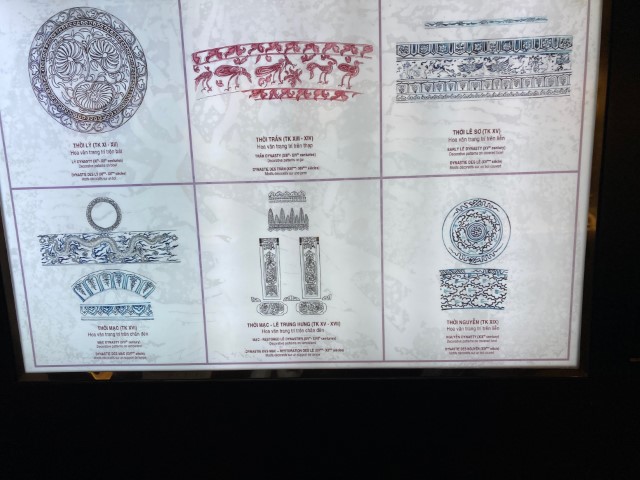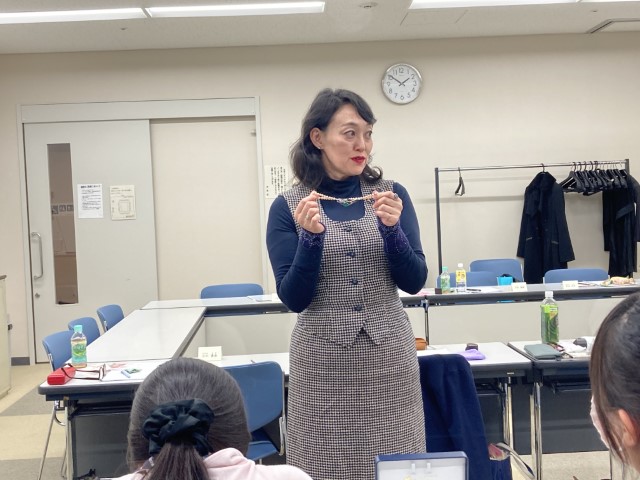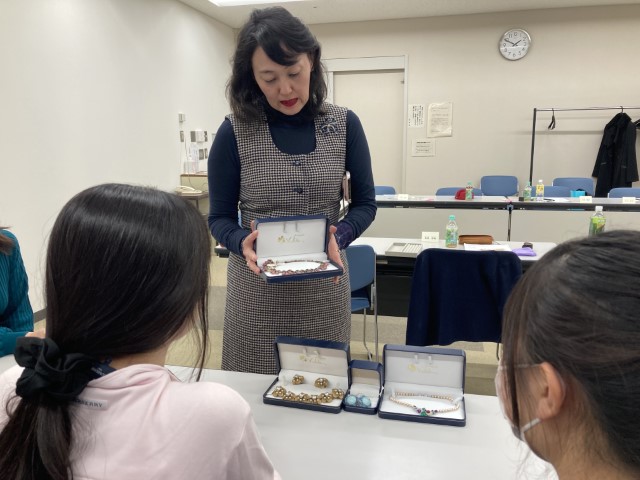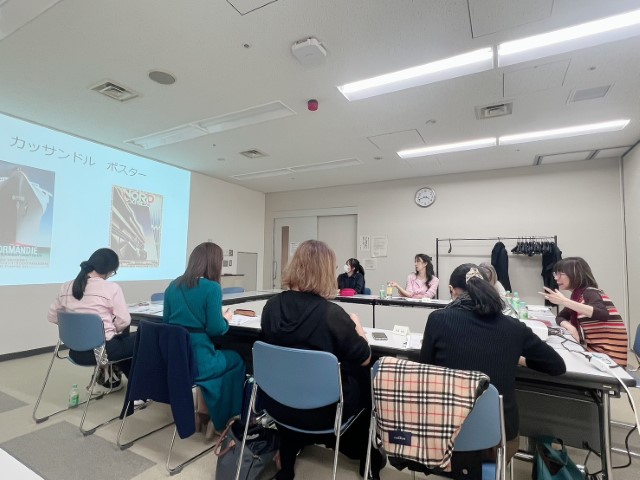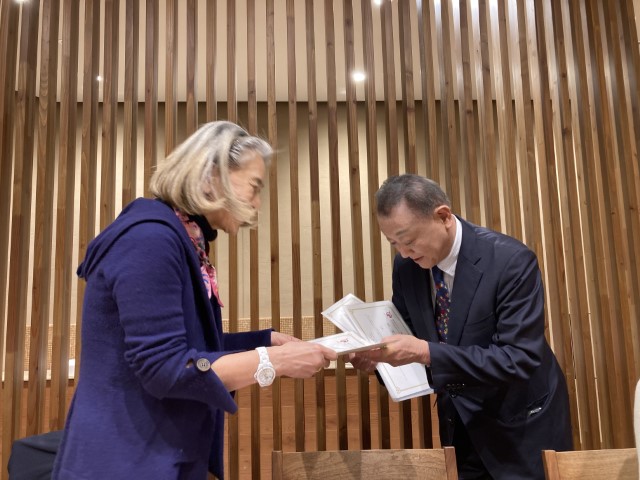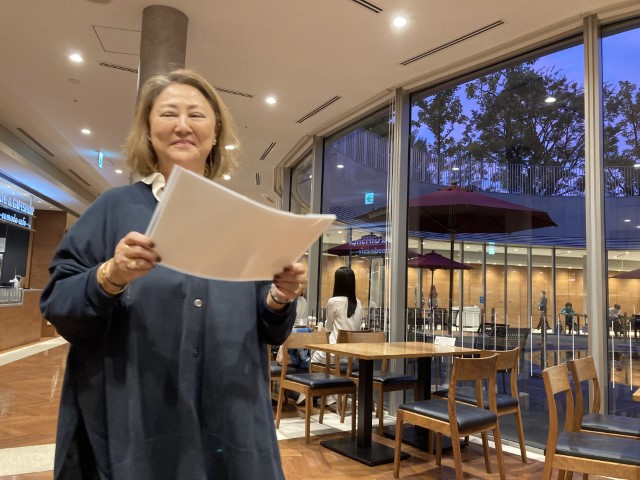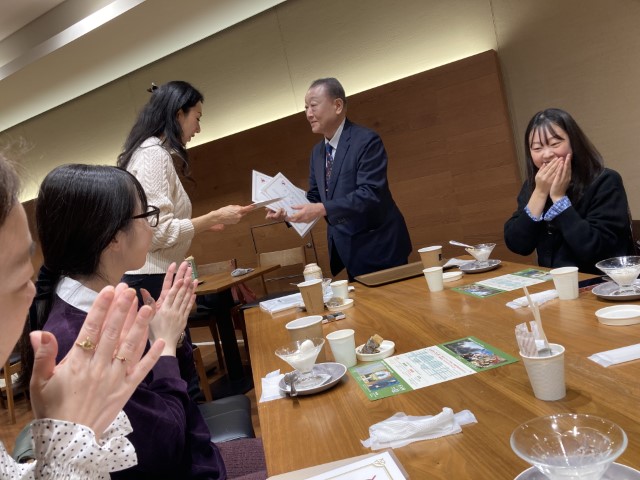大都会ハノイの街を知り尽くすのにはとても足りない日数ですが、後ろ髪を引かれる思いで次なる目的地へ向けて出発です。空港まで30kmの車窓からも、興味深い建築だらけな街。



今回は北部のハノイと南部のホー・チミンに加えて1泊だけ中部の街、ホイアンをプログラムに入れました。ベトナムという国を初めて訪れる人も多い中、いわゆる「東京と大阪の間にベトナム戦争の影響を受けていない古都があり、かつては貿易の街として栄え鎖国前の日本人も移住して日本人街があった、そして今やこのレトロで可愛い街並みが世界遺産となっている」と聞けば行かない手はありません、ユーラシア旅行社さんのご提案で研修の中抜きとして入れた癒しの街、ホイアン。ベトナム第3の都市、ダナンの空港より40分くらいで到着です。
この日は日本語を学んでいるというガイドさんをお願いしました。お名前はベトナム語の発音が難しいので「空」と呼んでください、ということで愛嬌のあるしっかり者の女性がダナン空港にお出迎え。やはり外国語は緊張して話すからか若干ぎこちない日本語イントネーションがAIっぽいので「AI空ちゃん」と親しみを込めたニックネームを付けてみなさんでお頼りさせて頂きました。


ダナンのNGON THI HOA でランチをいただき(ここもまたハノイに劣らず可愛い店構え、お料理も中部独特の食材などがあるようで、スタッフさんに食べ方を教わりながらトライ。手で巻いたり殻を外したりするのでビニール手袋も用意されていました)、いよいよホイアンの街へ入ります。スーツケースを詰んだ大型バスは市街地には入れないため、途中の駐車場で電気自動車に乗り換えてホテルまでの送迎です。この電気自動車、よくヨーロッパの街にもある観光用ミニ列車みたいな風貌をしているのですが、乗るとビュンビュン飛ばしてちょっと怖い!?





ホイアンのホテルも5星、ロイヤルホイアンMギャラリーという素敵なリゾートホテル。大きなバスタブが部屋の中にあり、ザ・コロニアルという雰囲気はロビーからも伝わってきます。
チェックイン後「本来は外観見学だけど17時までに着けば中にも入れる」ということで、福建会館をAI空ちゃんの解説にて見学。旧市街を歩きながらところどころで説明をいただき、行き着く先は日本人商人によって16世紀末に架けられたという来遠橋(通称日本橋)。










この辺りで日もすっかり暮れ、さすがに歩き通しで疲れてきたところで、機転の利くY添乗員の計らいで近くで予約している夕食のレストランへ交渉して休ませていただくことに。しばしの休憩タイムで足ツボマッサージを受けたり夜店の買い物に出かけたりした後、ディナーをいただきます。

なんだか食べてばかりのプログラムですが、種類も量も多いのに日本人好みのやさしい味なのか、食べられてしまう不思議。夕食中に降ったとされる雨も止み、夕涼みにふさわしくなった街から電気自動車のお迎えですぐ傍のホテルへ。今夜もぐっすり眠れそうですね。